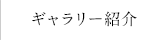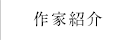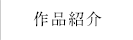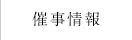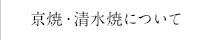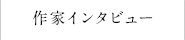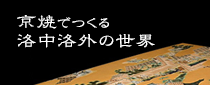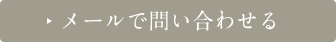作家インタビュー
西嶋秀樹Nishijima Hideki



角度によってさまざまな表情を見せる、天目のうつわ。そこにはきらきらと虹色の雲のような虹彩が輝いている。
この器の作者は西嶋秀樹さん。亀岡を拠点に、50年近くにわたり精力的に作陶を行っておられる作家だ。今回はそんな西嶋さんにお話を伺った。

西嶋さんは1948年に熊本県荒尾市に生まれ、3歳で京都の亀岡に移り住んだ。実家はごく普通の一般家庭で、身内にものづくりをしている人がいたわけではなかった。そんな西嶋さんが陶芸に出会ったのは、高校生のときだ。
「たまたま家の近所に陶芸の窯がありましてね、夏休みに手伝いに行っていたんです。ものをつくる楽しさに触れたのはそのときでした」
その後、高校卒業とともに西嶋さんは京都府立陶工職業訓練校に入学し、本格的に陶芸家の道へ進むことになった。
「高3になって進路を決めなきゃならんとなったとき、窯の手伝いをしていたら、どうだ、と何気なく誘われたんですよ。それで訓練校に入学手続きをしにいったんですが、実はそれが締切当日でした(笑)」
西嶋さんの長い陶芸家人生のはじまりは、なんともドラマチックなものだった。
当時、訓練校に入学した同期は18人ほど。ほとんどは実家が陶芸家や窯元という、まったくの外部からきた生徒は西嶋さんを含めて数人だったという。
「本当に何の知識もないまま飛び込みましたから、右も左もわからなくて。でも案外、他の皆も土を触ったことのない初心者ばかりでしたね。それに僕は何も知らない分、かえって気楽にやることができました」
西嶋さん自身、まともに自分で焼き物を作るようになったのは訓練校に入ってから。京焼・清水焼と他県の焼き物との違いもそのときに初めて知り、世界が広がったという。

「訓練校の先生の方針も「まずは基礎をみっちり」というものでしたから、土練りやろくろ、基本的な技術を覚えたらあとはもうひたすら数を作って学ぶという感じでした。
当時はまだ薪の窯を使っていましたが、その後ガスや電気に代わりましたので、訓練校でおそらく僕らが薪窯を経験した最後の世代でしょう。まるで窯元の職人集団みたいに、和気藹々として楽しい日々でした」
当時の西嶋さんは亀岡の自宅から学校のある清水まで、毎日SLで通っていたという。京都の市内で薪窯の使用が禁止される以前は、窯からの煙もよく見えたという。
訓練校を卒業後、西嶋さんは楽焼の作家である大野鳩行氏に師事した。こちらも偶然、アルバイトを募集していたところを誘われたのがきっかけなのだという。
楽焼は茶道用の抹茶碗を主に手がけるため需要が限られがちだが、西嶋さんが弟子入りした当時はちょうど茶道ブームが起き、楽焼の需要が非常に高まった時期だった。そのため西嶋さんたちは毎月何百個もの茶碗を作り続けていた。
「多い日で100個位、毎日茶碗を作り続けてましたよ。焼くときも同時にいくつも窯を動かして、数日ごとにローテーションで。とにかく売れたので、作らないと在庫が足らなくて」
しかし、この時のひたすら茶碗を作り続けた経験のおかげで、西嶋さんは大いに腕を磨くことができたという。
「同じものをたくさん作り続けることで自然と手が技を覚えることができました。ものづくりにおいて上達の秘訣は、とにかく数を作ること。ひとつのものをあれこれこねくり回していてもだめなんです。先生にも、良いものをたくさん作れ、だめなものは壊していいんだから、と教わりましたが、本当にその通りだと思います。今はなかなかそういうところが少ないですから、若い方は大変でしょう。それを思うと良い時代でしたね」
その後、西嶋さんは1972年には独立。窯を構えた自宅近くの通りから名をとった「柳窯」を開いた。しかし、当時西嶋さんはまだ20代前半と無名の若手。作品にはなかなか買い手がつかなかったという。転機が訪れたのは、独立から1年ほど経ってのことだったそうだ。
「ホテル東山閣(東山七条)で、洛東会(問屋向けの陶芸見本市)があるというんで、思い切ってそこに紹介してもらい、いくつか作品を出したんですよ。そうしたら初めて3件くらい買い手がついてくれて。それから洛東会をはじめお店やギャラリーなどに卸すようになりました」
その後、1978年に公募展で入選も果たし、西嶋さんは本格的に一人の陶芸家として歩みだしたのだった。


そんな西嶋さんは、個展やギャラリー向けに一点ものの作品を制作する傍らで、問屋向けの数を求められる作品も制作し続けている。忙しい時は数をこなすために同時に3基の窯を数日ローテで動かしていたという。当時に比べれば、今はペースはずっとゆっくりになってはいるそうだが、今後も異なる方針の作品を同時に制作するスタイルを続けていくつもりだそうだ。
「とにかくたくさん作らないと、腕がなまっちゃうからね。それに、仕事場にいるのが好きなんですよ。引きこもるのも平気で、一週間とかいられます。陶器屋っていうのは明るい引きこもりみたいなもんだと思いますよ(笑)」


西嶋さんが手がける作品は、楽焼のほか、粉引、伊羅保、天目など、一見同じ作家の作品とは思えないほど多彩だ。
西嶋さんの工房にはさまざまな焼物に対応できるよう、電気窯のほか、楽焼専用の小さなガス窯、炭窯など、色々な窯が揃っている。一部は登り窯の跡から耐火煉瓦を運び、自分で積んで拵えた手作りだ。窯の周辺に積み上げられたバケツにはそれぞれ異なる釉薬が入っており、その幅広い作陶ぶりを物語っている。


なかでも西嶋さんが長年取り組まれているものが、天目だ。
西嶋さんは独立して数年ほど経ったころから、天目を始めたという。
「最初に作った天目は油滴っぽい模様で、なんだか薄っぺらい感じでした。「青サバみたいだ」と言われたこともありましたね(笑)」
初期に作られた天目を近作と併せて見せていただいた。近作に比べると、初期作の方が金属釉の結晶の粒が少々大きい。天目はこの星のような結晶が出来を左右するが、細かくするには技術を要する。西嶋さんは、現在の作品のような細かな結晶を作り出すまでに、約10年を要したそうだ。
また、天目は微妙な温度変化で出来上がりが左右される、手間のかかる焼物だ。そのため量を作ることができず、西嶋さんの窯でも一度に入れる数は60個が限度。また、窯に入れる場所で火の当たり方や温度も変わるため、一度火を入れた後も途中で一旦火を落として器の位置を調整し、もう一度火を入れるという作業を3度ほど繰り返して調節する必要がある。そのため、焼き上がりまでには10日を要する。その日の天候で気温が変われば模様は変化し、同じものはひとつもできない。少しミスをすれば全滅することもある。しかし、そこが面白いのだと西嶋さんは笑う。
「1個いいものを作るのに300個くらいは失敗するもの。手間もコストもかかるけれど、ちょこちょこ温度調整をしたり位置を変えたりする作業自体が楽しいし面白いんですよ」

そして、西嶋さんの天目で目を引くのが、虹彩だ。虹彩は、さまざまな金属や金属酸化物を調合した釉薬を薄く施し、真珠貝のような光沢や色合いを生み出すもの。西嶋さんのそれは、用いた土や釉薬と窯焼きの際の条件が複雑に作用して生まれる「窯変」が重なり、金属的な輝きに天目の斑紋が相まって、どこか妖艶な、不思議な美しさを放っている。特別な金属を釉薬に加えているのでは? と思われることもあるそうだが、実際は一般的な素材しか使っていないという。西嶋さんはごく普通の素材を絶妙に組み合わせることで、この文様と色彩を生み出しているのだ。ここまでたどり着くには相当の時間が費やされていることは、想像に難くない。
なかでも出すのが難しいのが、紫色の虹彩だという。通常よりもほんのりと赤みを帯びた紫の虹彩は、1度の焼成で作れる60個の天目のうち、5個できるかどうかというレベルだそうだ。適正温度から10度変われば途端にその色は失われてだめになってしまうほどデリケート。しかしきちんと焼ききらないと器が締まらず緊張感が出ない。絶妙なバランスを探りながらの作業が求められる。
「調合は少しずつ変えながらやっていますが、うまくいくとは限らない。でも、釉薬もんは何度も試して失敗しないとだめなんです。失敗して調整をして、それを続けていくうちに使えるものや、その窯の具合などもわかってくるものですから」
また、最近では黒い素地に細かな結晶粒の模様を出すという表現も試みていらっしゃるという。これも難しい作業で、少しのミスで器は真っ黒になり、結晶粒は消え失せてしまう。美しいものはその作り方すら繊細なのだ。
それでも、西嶋さんはその難しさを苦労としてではなく、わくわくしてしょうがないといったように、実に楽しげに語られる。
「もともと数が目的じゃない作品を作るときは、最初からリスクは承知の上です。だって、安全なものばっかり作っていてもつまらないからね」
一点ものだからこそ、冒険ができる。その機会を西嶋さんは大いに楽しみながら、それでいて一心にものづくりに取り組んでおられる。その飽くなき挑戦心が伝わってきた。
「場所によって窯も使えるものと使えないものがあったりするし、それぞれやれることは違う。けれど、その制約のなかでどうやるか、如何に良いもの、新しいものを作れるかが、陶芸の面白みだと思うんです」
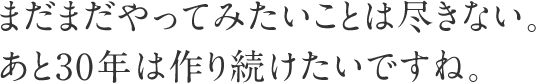


西嶋さんの新たな表現を生み出す試みは天目だけに留まらない。
例えば、西嶋さんは富士山や三宅島など全国各地の火山灰を集め、釉薬として用いることを試みている。
火山灰に含まれる成分は場所によってまったく異なるため、焼きあがったときの色や風合いもそれぞれ違う。ある山は緑、ある山は赤土色と、各山や土地の持つ個性が焼き物に現れるのだ。ちなみに、今まで試した中で西嶋さんが特に良い出来と感じたのは、長崎県・雲仙普賢岳のものだそう。ぽってりと濃い釉薬のかかり具合が、なんとも味わい深く良い風合いを出している。
「面白いでしょう。他に特別なものは何も混ぜていない。元の灰をちょっと乳鉢ですって糊を足して、そのまま使っているだけ。なのに、こんなに良い色が出ているんです。」
とにかく自然の素材は何でも試して焼いてみるという西嶋さん。なんと、日本のみならず海外からも素材を集めているという。見せていただいたのは、ハワイ・マウイ島にあるマレアカラ火山の岩石。西嶋さんは、これを手作業で少しずつ削り、粉状にして釉薬として用いているという。他にも、アメリカ・ワシントン州セントへレンズ山の火山灰 、カリフォルニア州サンタローザの砂漠の石や、オクラホマ州の名の由来になったという赤い土、などなど…西嶋さんの手元には遠くアメリカで収集した素材が多数。西嶋さんにとって、旅先の土や石こそが最高の土産なのだ。

「一口に灰や釉薬といっても、持っている色はさまざま。それに、使っている土や薬、形が同じものでも、使う窯で違うものができる。これが陶芸の奥深さ。だから面白いし、やめられないんですよね」
西嶋さんは今年(2017年)春にもアメリカ・オクラホマをたずねる予定だという。旅先でも、作陶のレクチャーを行うそうだ。またその際にも、新たな素材との出会いがあるかもしれない。楽しみで仕方ないんだ、と西嶋さんは語ってくださった。
「まだまだやってみたいことがたくさんあるので、自分のできる範囲でやってます。でも尽きることがないですね。今は68歳ですが、これからあと30年は続けますよ!」
そう言って笑う西嶋さんの表情は、好奇心旺盛な少年のように明るく輝き、御年を感じさせないほどのエネルギーに満ちていた。30年後といえばほぼ100歳。それまでにどのような挑戦をし、どのような器を生み出されるのだろうか。西嶋さんのこれからの活動を、楽しみにしたいものだ。
西嶋秀樹

- 1948年
- 熊本県荒尾市に生まれる
- 1951年
- 京都府亀岡市に移る
- 1968年
- 京都府立陶工職業訓練校修了
楽焼・大野鳩行氏に師事 - 1972年
- 独立開窯 柳窯
- 1978年
- 第7回日本工芸会近畿支部展 入選
- 1979年
- 第23回京都府工芸美術展 入選
- 1981年
- 第10回日本工芸会近畿支部展 入選
日本工芸会賞 受賞 - 1982年
- 第29回日本伝統工芸展 入選
- 1985年
- 第32回日本伝統工芸展 入選
- 1986年
- 第33回日本伝統工芸展 入選
- 1994年
- オクラホマ州立大学にてデモンストレーション
- 1995年
- オクラホマ州スティルウォーター市
Multigraphis Art Centerにてデモンストレーション - 2000年
- 第47回日本伝統工芸展 入選
日本工芸会正会員認定 - 2001年
- 第48回日本伝統工芸展 入選
- 2002年
- 第49回日本伝統工芸展 入選
- 2006年
- カリフォルニア Rio Del Marにてデモンストレーション
代表作
-

引出灰釉 花筒
-

虹彩釉 花生
-

虹彩釉 茶碗